対象者別
所属
領域
看護学部
大学院

百瀬 由美子ももせ ゆみこ
教授 学長
在宅看護学、老年看護学

山田 聡子やまだ さとこ
教授 学部長
基礎看護学領域

長谷川 喜代美はせがわ きよみ
教授 研究科長
公衆衛生看護学

岡田 摩理おかだ まり
教授 学術情報センター・ 図書館長
小児看護学領域

下間 正隆しもつま まさたか
教授
専門基礎

森田 一三もりた いちぞう
教授
専門基礎

高見 精一郎たかみ せいいちろう
助教
専門基礎

鈴木 寿摩すずき すま
准教授
一般教養

松崎 久美まつざき くみ
准教授
一般教養

南谷 志野なんや しの
教授
看護管理学領域

田中 慎吾たなか しんご
講師
看護管理学領域

巻野 雄介まきのゆうすけ
准教授
基礎看護学領域

竹内 貴子たけうちたかこ
講師
基礎看護学領域

大西 幸恵おおにし ゆきえ
講師
基礎看護学領域
-scaled.jpg)
高下 翔たかした しょう
助教
基礎看護学領域
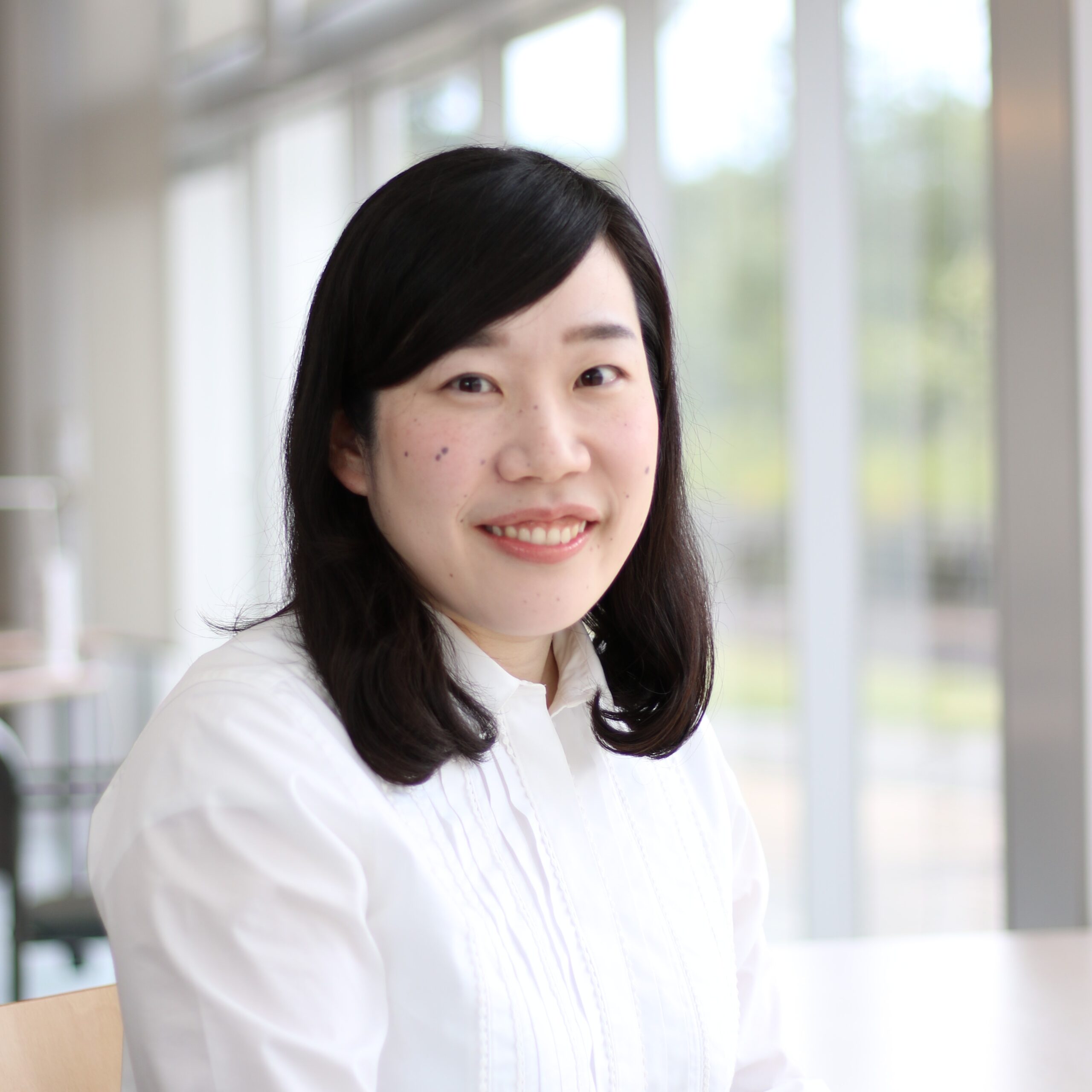
福岡 友理恵ふくおか ゆりえ
助教
基礎看護学領域

松原 由希子まつばら ゆきこ
助教
基礎看護学領域

山中 大輔やまなか だいすけ
助手
基礎看護学領域

カルデナス 暁東かるでなす しゃおどん
教授
成人看護学領域

石黒 千映子いしぐろ ちえこ
准教授
成人看護学領域

栩川 綾子とちかわ あやこ
准教授
成人看護学領域

渡邉 直美わたなべ なおみ
講師
成人看護学領域

田口 栄子たぐち えいこ
助教
成人看護学領域

谷口 純平たにぐち じゅんぺい
助教
成人看護学領域

石田 咲いしだ えみ
助教
成人看護学

石原 佳代子いしはら かよこ
助教
成人看護学領域
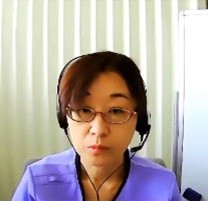
中島 佳緒里なかじま かおり
准教授
災害看護学領域

藤井 愛海ふじい めぐみ
准教授
災害看護学領域

長尾 佳世子ながお かよこ
講師
災害看護学
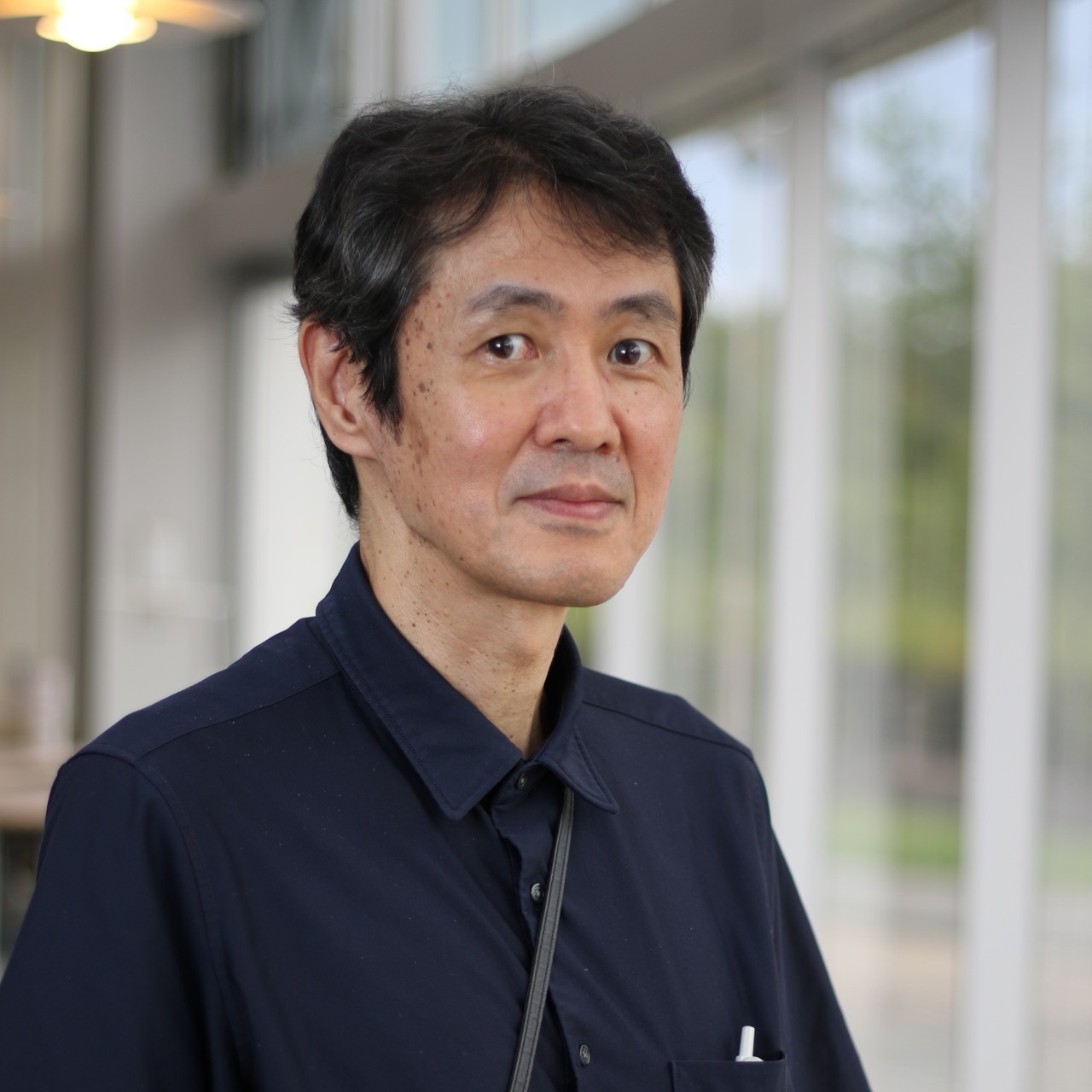
小林 尚司こばやし なおじ
教授
老年看護学

清水 みどりしみず みどり
准教授
老年看護学領域

天木 伸子あまき のぶこ
准教授
老年看護学領域

近藤 香苗こんどう かなえ
講師
老年看護学領域

段 暁楠だん ぎょうなん
助教
老年看護学領域

深谷 由美ふかや ゆみ
准教授
在宅看護学領域

大林 実菜おおばやし みな
講師
在宅看護学領域

宝木 百代たからぎ ももよ
助手
在宅看護学領域

野口 眞弓のぐち まゆみ
教授
母性看護学

岡津 愛子おかつ あいこ
准教授
母性看護学領域

千葉 朝子ちば あさこ
講師
母性看護学

草深 真菜くさぶか まな
助手
母性看護学領域

神道 那実じんどうなみ
准教授
小児看護学

遠藤 幸子えんどう さちこ
講師
小児看護学
.jpeg)
神谷 美帆かみや みほ
講師
小児看護学領域

鳥居 賀乃子とりい かのこ
助教
小児看護学領域

河野 由理かわの ゆり
教授
精神看護学領域

原田 真澄はらだ ますみ
准教授
精神看護学領域

飯田 大輔いいだ だいすけ
講師
精神看護学領域

清水 美代子しみず みよこ
准教授
公衆衛生看護学領域

大森 美保おおもり みほ
講師
公衆衛生看護学領域

伊藤 明子いとう あきこ
特命教授 / キャリア支援室長

百瀬 由美子ももせ ゆみこ
教授 学長
在宅看護学、老年看護学

山田 聡子やまだ さとこ
教授 学部長
基礎看護学領域

長谷川 喜代美はせがわ きよみ
教授 研究科長
公衆衛生看護学

岡田 摩理おかだ まり
教授 学術情報センター・ 図書館長
小児看護学領域

森田 一三もりた いちぞう
教授
専門基礎

南谷 志野なんや しの
教授
看護管理学領域

田中 慎吾たなか しんご
講師
看護管理学領域

巻野 雄介まきのゆうすけ
准教授
基礎看護学領域

カルデナス 暁東かるでなす しゃおどん
教授
成人看護学領域

栩川 綾子とちかわ あやこ
准教授
成人看護学領域
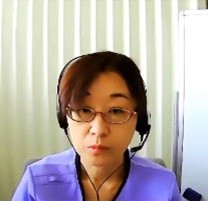
中島 佳緒里なかじま かおり
准教授
災害看護学領域

藤井 愛海ふじい めぐみ
准教授
災害看護学領域
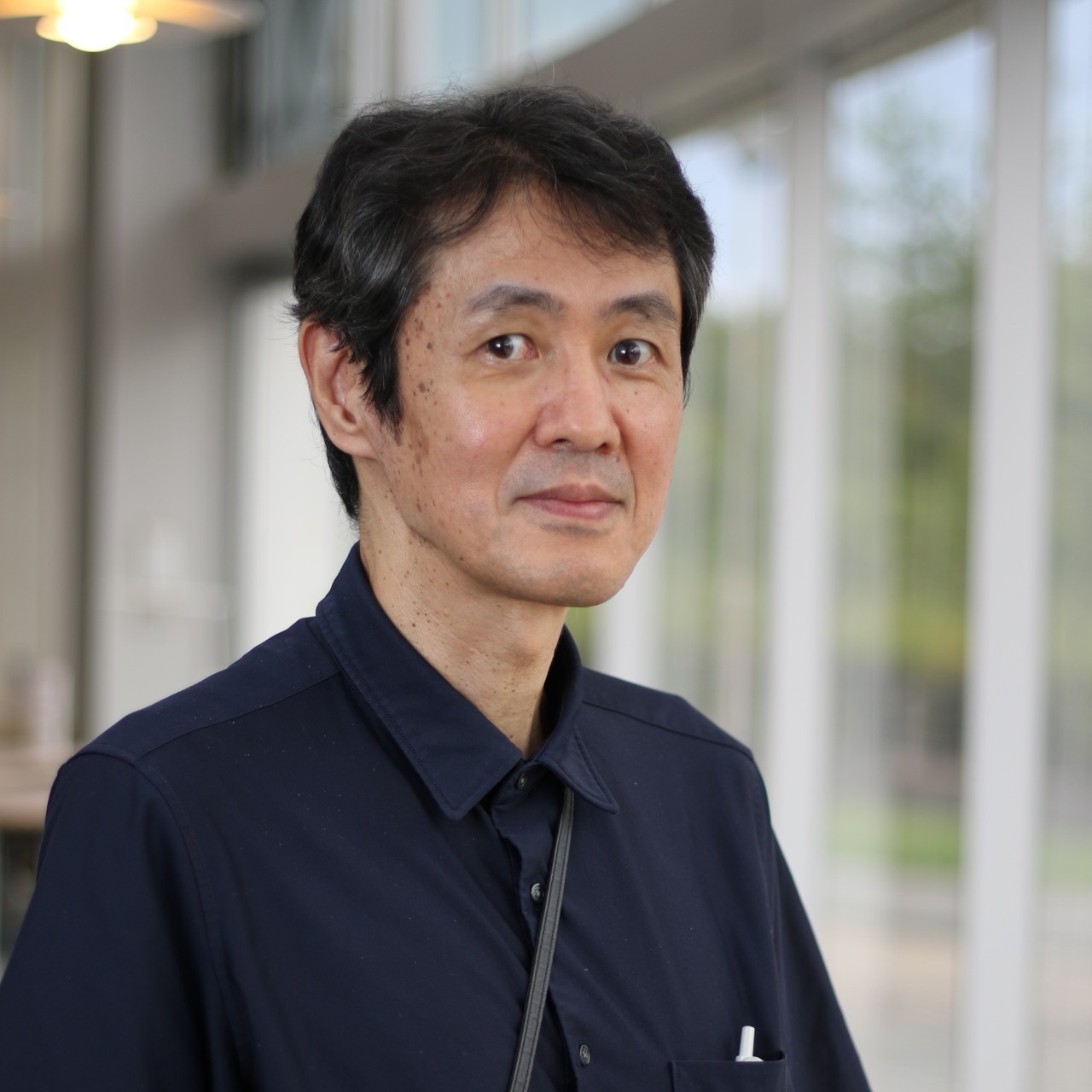
小林 尚司こばやし なおじ
教授
老年看護学

清水 みどりしみず みどり
准教授
老年看護学領域

天木 伸子あまき のぶこ
准教授
老年看護学領域

深谷 由美ふかや ゆみ
准教授
在宅看護学領域

野口 眞弓のぐち まゆみ
教授
母性看護学

岡津 愛子おかつ あいこ
准教授
母性看護学領域

神道 那実じんどうなみ
准教授
小児看護学
看護管理独自の理論や知識をミクロ・マクロの視点から探求し、現場の課題や政策に関する課題について、 看護管理者の経験を有する専任教員が研究および実習指導を行います。 また、「認定看護管理者コース」は、認定看護管理者の資格認定取得を目指し、体系的に看護管理学を学べる プログラムとなっています。 このプログラムでは、講義や学生による発表・討議だけでなく、人的資源管理、安全管理、財務管理をテーマに した約3か月ずつの臨地実習を通じて、認定看護管理者に求められる組織分析力や交渉術を養うことができます。
南谷志野
組織行動・心理、人材育成・活用、人事・労務管理、医療安全等に関する課題に対して、質的・量的手法を用いて 探求していきます。
看護管理者を中心に、全ての看護職を対象とした研修を行っています。
看護管理者に限らず、幅広い年代や職位の方々とのグループダイナミクスを大事にしながら、教員と学生が相互に学び合いたいと思っています。

看護教育・技術学領域は、大きく揺れる時代の波によって変化し続ける社会のニーズに柔軟に対応した 看護教育のあり方やケアサイエンスの構築を模索できる人材育成を目指します。斬新なアイデアは大歓迎です。 これまでの慣習にとらわれず、幅広い視野で看護教育の方法を検討し、発展的で実証的な看護技術の開発に 取り組んでいきましょう。 「看護技術を見直したい!」、「これまでの看護実践は正しいのだろうか?」、「どうすれば看護師としての 教育はうまくいくのだろうか?」など、日ごろの日常業務や実践内容への疑問、新人育成や臨地実習指導などの 経験から生じた疑問は研究への第一歩です。研究を通して解決の糸口を探求しませんか。
山田聡子 巻野雄介
看護基礎教育および継続教育や人材育成に関する課題、看護技術に関する課題、看護倫理に関する課題の探求を、量的・質的な手法を用いて取り組めるよう支援していきます。
看護職を対象にセミナーを開催しています。
2024年度のセミナー:専門職向け研修会「看護に役立つポケットエコーを使ってみよう」(10月開催)
本学卒業生や看護管理者、教育者など様々な経歴をもつ方々が在籍しています。これまでの実践を客観的に振り返る機会にもなり、自分自身の視野が大きく広がります。是非チャレンジしてみてください。
(写真は領域ゼミ(対面とオンラインのハイブリッド形式)の様子です)

私たちの領域は、周術期にある患者やクリティカルケアを必要とする患者の回復過程および家族に対する看護、慢性の病いをもつ患者とその家族に対する看護を探究します。対象となる患者および家族は、生涯にわたって長期間の療養を要し、苦痛や危機的な状況におかれることから、危機理論、ストレス・コーピング理論、病みの軌跡、セルフケア理論などの理論や概念を学びながら、臨床看護に必要とされる看護を探求します。
東野督子 カルデナス暁東 石黒千映子
公開講座として成人病に関連した項目、「高血圧を予防するための減塩のための工夫」「味わうことは健康のもと」「生活習慣を見直そう」など開催している。また、口腔ケアアンバサダーとして健康を維持する第一歩である口腔ケアの啓発に尽力している。
さらに、「メイクセラピー講座」「カラー(色)を楽しむ講座」などを通して、地域住民がより楽しく社会参加できるよう活動している。
授業ではプレゼンテーションとディスカッションを中心にしながら、さまざまな理論を学ぶとともに、患者の回復過程や生活の再構築に必要な看護を探求するための方法を学びます。

母性看護学領域では、周産期および女性のライフサイクル全般にわたる健康課題に関する研究を得意とします。
「母性看護学特論」で、研究の動向を理解し、研究疑問(リサーチクエッション)を構造化し、文献検索を行います。
さらに、得られた文献を批判的に検討します。周産期および女性のライフサイクル全般にわたる課題を解決するための基礎的能力を養うために「周産期ケア開発特論」と「ウィメンズヘルス特論」を学びます。
「母性看護学演習」で、学生が関心をもつ領域での参加観察、インタビューなどを通じ、対象理解を深め、学生が関心をもつ領域の現象の分析を行います。これらの学習を通して、研究を進める準備をします。
野口眞弓
科学研究費の交付を受けて、「育児をする父母のソーシャル・キャピタルを醸成するアクション・リサーチ」、「周産期うつ・不安のハイリスク妊婦に対する認知行動療法的介入プログラムの開発と評価」を行っています。
豊田市「子どもにやさしいまちづくり推進会議」会長、高浜市「母子保健医療ネットワーク会議」委員
助産師の資格が有り、実務経験が3年以上ある方は、大学院に入学できます。
周産期および女性のライフサイクル全般にわたる健康課題を解決するためのケア開発をご一緒にしてみませんか。
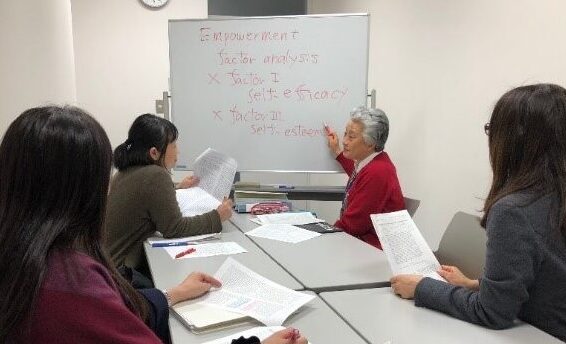
近年、子どもと家族を取り巻く環境の変化は著しく、社会的な支援がさらに必要とされる時代の中、小児に関わる看護職は病院のみならず学校や保育所はじめ訪問看護ステーションなどの地域での活躍が期待されるようになりました。本学の小児看護学領域では、個々の対象の特性や状況に合わせた看護を提供するための方策を追求しています。
それぞれの場での課題を多側面から考え、子どもと家族のより豊かな生活を目指した研究課題に取組んでいます。
そのためには、広い視野と深い思考力が必要です。学生同士や教員とのディスカッション・プレゼンテーションを通して、切磋琢磨していく楽しみを感じられる授業やゼミを行います。また、小児看護専門看護師としてリーダーシップをとっていく高度実践家の養成もしています。
岡田摩理 神道那実
指導教員は、医療的ケア・重症心身障害や発達障害および慢性疾患をもつ子どもと家族の支援、プレパレーション、子育て支援、小児看護学の基礎教育に関する研究を行ってきました。
小児と家族に関する研究課題全般を支援します。
これまで、子育て中の保護者への研修会や保育所看護師対象の専門職向け研修会などを実施してきました。
現在は、急病やケガなどの対応について一般向け動画公開をしています。
なお、指導教員は、看護系学会の役員・論文査読委員や公的団体の会議のメンバーとしても活動しています。
子どもと家族を支援する上での課題を解決したいという思いをもった人を歓迎します。身近な動機から始まる研究疑問でも、現象を丁寧に分析し、研究的に追及していくことで解決の道が開かれます。一緒に悩みながら考えていきたいと思っています。

私たちの領域は、老化や疾病により日常生活に困難がある人のその人らしい生活を支えることを目標にして、実践・教育・研究に取り組んでいます。
百瀬由美子 小林尚司 清水みどり 天木伸子 深谷由美
療養病床や特別養護老人ホームおよび自宅など療養・生活の場における看護に関する研究、療養と生活を支える多職種連携に関する研究を主なテーマとしています。
在籍中の大学院生は、地域の介護支援専門員の立場から、医療との連携を研究しています。
豊田市訪問看護師育成センター講師 市民講座「知って安心、認知症」
老年・在宅看護の領域では、健康問題以外にも対象者の生活や人生の送り方が看護上の課題となることで、「看護のあり方」について臨床や教育の場で迷い悩むことが多いと思います。そこで大切なのが「その人らしさ」の尊重だと思います。私たちは、その人らしさは、目に見える生活の様子だけでなく、その背景にあるその人の関心こそが大切と考えています。対象者の関心に気づき・尊重できる力を、ともに培っていきたいと思います。

精神的な健康課題をもつ人の全人的健康を保持・増進するうえで重要となる環境を治療的観点から捉え直し、精神状態をアセスメントするための根拠となる看護理論を基盤に、治療的コミュニケーションを含む卓越した看護実践を展開できる高度実践看護師を育成します。加えて、メンタルヘルス、リエゾン領域における多様な研究課題に取り組んでいます。
原田真澄
地域や医療施設で療養生活を営む精神的な健康課題をもつ人への看護に関する研究や、家族への支援に関する研究などに取り組んでいます。
精神看護学は、「人間とは何か」「病とは何か」ということを深く考えることが出来る分野です。
心の病をもつ人の言葉にならない心の深層にある認識に寄り添う看護の技を一緒に探究していきたいと思います。

地域看護活動は、地域において、個人・家族・特定集団・地域を対象とし、健康の維持増進、疾病予防、早期発見・早期治療・リハビリテーション・ターミナルなど様々な健康レベルへの支援を看護の専門的立場から展開する看護活動であり、働きかけの対象や活動内容は幅広く多岐にわたります。また、地域の生活において健康問題を解決するため、健康課題を構造的に捉えること、様々な関係者と連携・協働し組織的に活動することが求められます。このような地域看護活動について、効果的な看護実践を探求していきたいと考えています。
長谷川喜代美 森田一三 清水美代子
長谷川喜代美:地域看護領域、特に行政分野の保健師の活動に関する課題
森田一三:地域看護学領域、特に行政機関、地域住民による地域保健活動に関する課題、および口腔の健康と全身の健康に関連する課題
清水美代子:地域看護領域、特に産業分野の保健師の活動に関する課題
公開講座
「自分のからだを知ろう 宮口一色健康測定会」
[行政委員会等]
長谷川 喜代美:
豊田市地域保健審議会委員
みよし市介護保険運営審議会委員
みよし市地域包括支援センター運営協議会委員
みよし市地域密着型サービス運営審議会委員
森田 一三:
名古屋市学校歯科医会顧問
清水 美代子:
日進市介護認定審査委員会委員
みよし市保健対策推進協議会委員
豊田市健康づくりプラン(第四次)策定委員
[学会委員会等]
長谷川 喜代美:
日本赤十字看護学会専任査読委員
森田 一三:
日本公衆衛生学会代議員
日本学校保健学会代議員・編集委員
日本歯科医療管理学会編集委員
東海学校保健学会評議委員・編集委員長
清水 美代子:
愛知県看護協会学会委員
誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることのできるケア体制づくりが益々重要になっています。
地域の人々の健康問題を明確にし、課題解決するための効果的な活動方法について共に考えてみませんか。
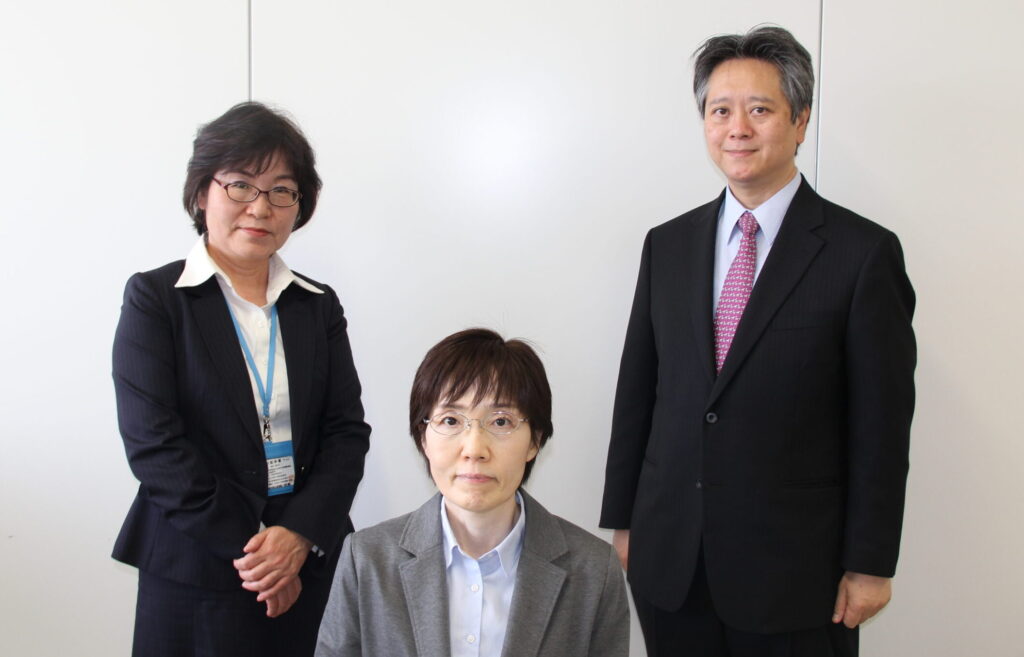
本領域は、2015年大学院看護学研究科看護学専攻修士課程に災害看護学として設置され、これまでに3名の方が修了されています。国内外で発生する災害という現象における医療・看護活動には、看護職への期待と共に自律して判断し、行動することが求められます。そのため、赤十字の人道を基盤に災害の全過程において被災者をはじめ支援を必要とする人々を個として集団として捉えた看護ケアの提供や、災害に関わる組織や専門職・住民と連携した防災・減災活動について主体的に学び、さらに自身の研究課題について探究して行きます。授業では、特に赤十字の関連施設や他施設の協力により救護員研修、防災訓練への参加などの機会を得て教育を行っています。
災害過程における看護活動に関連する課題(災害への備え・防災教育、災害看護経験に存在する知識)、および赤十字の災害看護,災害看護学教育に関する課題
本領域では、地域連携委員会との連携で、以下の貢献をしています。
豊田市高等教育活性化推進プラットフォーム事業「社会人防災マイスター養成講座」
公開講座「AEDを知ろう」
災害リスク削減や発災時に看護職が活動することが期待されていますが、災害看護学の教育は、これからその知識が蓄積されていく段階です。災害看護の実践経験や、現在災害看護についての疑問を、研究という活動を通して探究し再考してみることは、災害看護学への貢献と共に、今後のご自身にとって有意義な経験であろうと考えています。

専門基礎
一般教養
看護管理学
基礎看護学
成人看護学
災害看護学
老年看護学
在宅看護学
母性看護学
小児看護学
精神看護学
公衆衛生看護学